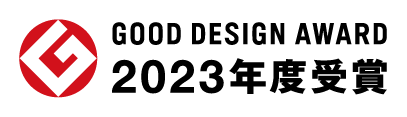-

- 移住者の施設から、みんなの居場所へ。白石市「109-one」が築く交流拠点
- 文:高木真矢子 写真:阿部一樹
移住してきたばかりの人も地域で暮らす人も、気軽に立ち寄りお茶を飲みつつ、誰かと話せる場所があったら——。
そんな願いから生まれた施設が、宮城県白石市にあります。白石市移住交流サポートセンター「109-one(トークワン)」。2018年5月、白石市の中心部にある商店街の一角にオープンしました。
109-oneで温かな場づくりを目指し奮闘する、移住交流コーディネーターの太斎沙織さんと阿部名央子さんにお話をうかがいました。
View more
-

- 島の絆が守りつなぐ「焼尻めん羊まつり」
- 文:三川璃子 写真:原田啓介
北海道羽幌町の離島・焼尻島で1982年から開催されてきた「焼尻めん羊まつり」。40年以上続くおまつりは、島を想う人々によって支えられてきました。
年々人手不足が深刻化する、まつりの運営。コロナ禍では中止を余儀なくされました。島でのめん羊飼育は、餌の仕入れや肉の輸送に大きなコストが。
それでも「焼尻島のサフォーク羊のおいしさをもっと知ってほしい」という人々の強い思いが、この文化を守り続けています。
View more
-

- 【ニセコ町長インタビュー】創造的摩擦が生み出すニセコのイノベーション
- 取材:中村敦史 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子
北海道が世界に誇るリゾート地「NISEKO」。世界中から毎年多くの人々が訪れるこの地は、かつて危機に直面しました。窮地から脱し、通年型リゾートへと変貌した背景には、住民と役場それぞれの主体的な働きがありました。
挑戦の息吹が宿るニセコ町のまちづくりについて、片山健也 ニセコ町長にお話をうかがいました。
View more
-

- 歴史を未来へのエネルギーに。三笠市から伝播する石炭の新たな可能性
- 文:本間 幸乃 写真:斉藤 玲子
燃える石「石炭」の発見から開拓されたまち、三笠。炭鉱が閉山し、多くの人が去った今もなお、地下には約7.5億トンの石炭が眠っているとされています。
この豊富な資源を活用できないか?という思いからスタートしたのが、三笠市「H-UCG(ハイブリッド石炭地下ガス化)事業」。かつてまちの発展を支えた石炭から、新たな産業とエネルギーを生み出そうという取り組みです。
地域再生をかけた事業への想いとこれまでの歩みについて、三笠市役所産業開発課の能瀬博隆さん、竹内翔平さんにお話をうかがいました。
View more
-

- 【白石市長インタビュー】教育改革と市民の挑戦が紡ぐ、未来を創造するまちづくり
- 取材:中村敦史 文:高木真矢子 写真:阿部一樹
蔵王連峰のふもと、古来から交通の要衝として繁栄を築いてきた、宮城県白石市。
人口約3万1000人の白石市は他の地方都市同様、人口減少という大きな課題に直面する中、「挑戦」をキーワードに独自の取り組みを展開しています。
takibi connectではこれまで、地域へのアツい思いを持った白石市の挑戦者を取材してきました。今回は特別編として、現在進めている教育改革と白石の人々に宿る挑戦魂について、山田裕一 白石市長にお話を伺いました。
View more
-

- 【三笠市長インタビュー】炭鉱のまち三笠が“再生”から見出す希望の光
- 取材:中村敦史 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子
かつて炭鉱都市として栄えた北海道 三笠市。北海道最初の鉄道全通や電話開通、上水道の設置がおこなわれた地域でもあります。炭鉱が閉山してもなお、三笠の人々に宿る挑戦の炎は消えていません。
takibi connectではこれまで、地域に根ざし活躍してきた三笠市の挑戦者を取材してきました。今回は特別編として、「再生」をテーマに挑む三笠市のまちづくりについて、西城 賢策 三笠市長 にお話をうかがいました。
View more
-

- 町民の命と絆を守る。みんなでつくる小清水町新庁舎「ワタシノ」
- 文:三川璃子 写真:小林大起
「久しぶり〜」と、コーヒーを片手にテーブルを囲み、ワイワイとお喋りする女性たち。カフェでよく見かけるシーンですが、これは小清水町役場の庁舎内での光景です。
2023年5月にオープンした小清水町役場の新庁舎「ワタシノ」は、官民連携で生まれた全国でも新しい複合庁舎です。テーマは、町民を守る「防災」と「地域の絆の再生」。2021年から新庁舎立ち上げに携わる地域活性化起業人・本城和彦さんにお話をうかがいました。
View more
-

- 頭と地球を守る。猿払を救ったホタテから生まれたHOTAMET
- 文:三川璃子 写真:原田啓介
「猿払といえばホタテ」と言われるほど、国内でも最大級の水揚げ量を誇る猿払村。しかしながらその裏では、毎年約1万トンにもおよぶ貝殻が水産系廃棄物として発生。猿払村では長年にわたって処理方法を模索してきました。
そうした中、2022年12月にスタートしたのがホタテの貝殻を再利用した環境配慮型ヘルメット「HOTAMET(ホタメット)」のプロジェクトでした。
「ホタテの貝殻が頭を守り、地球を守る」ーー地域課題と社会課題を解決するプロジェクトの一翼を担った、猿払村役場伊藤 浩一 村長と建設課の新家拓朗さんにお話をうかがいました。
View more
-

- まちの美しさは農業の賜物。一丸で高める美瑛小麦の価値
- 文:三川璃子 写真:小林大起
北海道美瑛町といえば、四季彩の丘やセブンスターの木など、有名な観光スポットを思い浮かべる人も少なくないでしょう。丘に広がるパッチワークのように美しい畑の景色は、思わず息を飲んでしまうほど。
View more
-

- 【恵庭市長インタビュー】思いの種を育み咲かせる、市民主体のまちづくり
- 取材:中村敦史 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子
欲しい未来はみんなでつくるまち、北海道 恵庭市。
主体的で熱意あふれる人々の力によって、花のまち・読書のまちなど、独自の取り組みを行い、人を惹きつけるまちとして成長をつづけています。
takibi connectでも、地域に根ざし活躍してきた恵庭市の挑戦者を取材してきました。今回は特別編として、市民と自治体が二人三脚で作り上げてきた恵庭市のまちづくりについて、原田 裕 恵庭市長 にお話をうかがいました。
View more
-

- IoT推進で叶える3年目の実り。猿払で生まれたストーリーを育む
- 文:三川璃子 写真:原田啓介
猿払に新しい産業をつくるため、2020年にスタートした施設園芸栽培調査研究事業。takibiconnectとしての取材は2022年で3回目です。
View more
-

- 今ある地域資源を生かす。小清水町が生み出すアウトドアと地方の可能性
- 文:三川璃子 写真:小林大起
山、川、海、湖の全てが揃う北海道でも珍しいまち、小清水町。四季折々300種類以上の鳥が見られることから、“野鳥の楽園”とも言われています。
静けさが広がる夕暮れ。湖のそばを歩くと、いつもは雑踏で聴こえない鳥の羽音もよく聴こえます。鳥たちが住む世界にお邪魔させてもらっているような気分です。
View more
-
- 「観光は人」雄武町観光協会があるもの活かして届ける地域の魅力
- 文:髙橋さやか 写真:高橋洋平
風にそよぐ緑の牧草、のんびりと草を食む牛たちの姿、その先に見えるのはオホーツク海。
北海道北部のまち・雄武(おうむ)町には、北海道らしい自然あふれる景色が広がっています。
雄武町には大きな娯楽施設はありませんが、地域にあるものを生かし、まちの魅力を届けている人がいます。生まれも育ちも雄武町という、三浦富貴子さん。雄武町観光協会職員として、人とのつながりを大切にしながら、雄武町ファンを増やしています。
View more
-

- 絶滅危機からの復活。まちをあげて取り組む、羽幌町海鳥保護の奇跡
- 文:三川璃子 写真:原田啓介
オロロンラインに沿って海を眺めながら羽幌町へ向かう道中、大きなペンギンのような鳥のモニュメントが出迎えてくれます。羽幌町のシンボル「オロロン鳥(ウミガラス)」と呼ばれる海鳥です。
世界でも有数の海鳥の繁殖地である羽幌町。ですが、2000年代にはウミガラスの数が10数羽まで減少する危機的状況にありました。
「鳥を守るには“対自然”ではなく、“対人”で考えなきゃいけない」ーーそう想いを語ってくれた北海道海鳥センターの石郷岡卓哉さん。海鳥絶滅の危機から、復活までの道のりをうかがいます。
View more
-

- 白石のササニシキを再び全国に。世代を超え伝統を未来へ
- 文:高木真矢子 写真:平塚実里
コシヒカリ・ひとめぼれ・あきたこまち・・「米」とひと口に言っても、その種類はさまざまです。かつて「東の横綱」とも言われた銘柄米「ササニシキ」。1993年に起こった大冷害以降、冷害や病気に弱いササニシキは作付面積が減少し、宮城県内での作付面積割合は約6%と、風前の灯となっています。
希少価値の高いササニシキを再び全国に届けようと、宮城県白石市では2016年3月から「宮城白石産ササニシキ復活プロジェクト・畦かえる」がスタート。プロジェクトに関わる白石市農林課農業振興係係長の髙橋由桂さんと、プロジェクト事務局として生産者や地元企業をつなぐ大槻育美さんに話をうかがいました。
View more
-

- まちのシンボルから広がる文化と歴史の輪。白石城再建と鬼小十郎まつりの物語
- 文:高木真矢子 写真:平塚実里
奥羽山脈と阿武隈高地に囲まれた白石盆地の中にあり、古来から交通の要衝であった白石市。まちのシンボルである白石城は、戦国武将・伊達政宗の腹心として有名な片倉小十郎の居城で、1874年に「明治の廃城令」で解体されました。
1995年、解体から120年余りの時を経て復元された白石城。復元への道のりと、白石城のふもとで毎年開催される「鬼小十郎まつり」について、お話をうかがいました。
View more
-

- 廃校を再び人々が集う場に。ひとくらすという希望の種火
- 文:高木真矢子 写真:吉成美里
阿武隈地域の豊かな緑と清らかな水の流れる石川町の山間部。
2021年4月、この地域にレンタルオフィスや会議室を備えた体験型宿泊施設「ひとくらす」がオープンしました。2015(平成27)年3月に閉校した旧中谷第二小学校の校舎を、町及び地元の有志らが約5年の歳月をかけ、利活用について模索・改修。新たに命を吹き込みました。
「ひとくらす」という小さな種火を絶やさぬよう静かに、確かな熱さを胸に前を向き続ける、この地で生まれ育った3人に話をうかがいました。
View more
-

- はなふるから始まる、次世代につなぐ花のまち・恵庭
- 文:髙橋さやか 写真:斉藤玲子
花には人の心を安らかにする不思議な力がある。
人々が混乱の最中にあっても、芽を出し、葉をしげらせ、花を咲かせ、生を全うして散っていく。その儚くも力強い、花の姿に心を惹かれるのかもしれません。
View more
-

- IoTの力で未来へ繋がる産業を。村民とともに創る「誇れる」作物
- 文:三川璃子 写真:原田啓介
「いちごの産地として猿払村の名前が広がって欲しい」ーー雇用を増やし、人口減少に歯止めをかけるため、猿払村でIoT推進事業が始動。その第一歩として、いちご、葉物野菜の栽培(施設園芸栽培調査研究事業)が2020年にスタートし、未来に向けて大きな一歩を踏み出しました。
2021年の取材から1年。最新技術を駆使した野菜・いちごの栽培はより本格的な動きになっています。新たなメンバーも加わり、形を変えながら挑戦の幅を広げるIoT推進事業。地域おこし協力隊の塚田治幸さん、坂入亮兵さん、藤田旅人さん、企画政策課小高翔太さんにお話を伺いました。
View more
-

- 閉校をチャンスに変えた「三笠高校生レストラン」という一筋の光
- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子
三笠から「食」のプロフェッショナルを。
かつて炭鉱で栄えた三笠市は、三笠高校を基軸に「食」をテーマにした新たなまちづくりのモデルを描いています。
道内の公立高校では初めて、食物調理科の単科校を設置。「食」への理解を深める教育を行い、生徒が腕を磨くための研修施設「三笠高校生レストラン MIKASA COOKING ESSOR(エソール)」を2018年にオープン。注目を集めています。
地域の活性化と生徒たちの成長を裏で支える、三笠高校調理部顧問の斎田雄司さんと製菓部顧問の鈴木多恵さんにお話を伺います。
View more
-

- 消滅可能性都市から若き挑戦者が集うまちへ。全力で挑む移住促進
- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙
宮城県の最南端。阿武隈高地に囲まれ、美しい山々と阿武隈川の雄大な渓流の眺めに心穏やかになる丸森町。
自然豊かなこの町は、少子高齢化や若い世代の流出が著しく、2014年には「消滅可能性都市」※に指定されるなど、人口減少の大きな課題を抱えています。課題解決へと大きく舵を切り、地域おこし協力隊を活用した移住促進施策へと踏み出した、丸森町。地域おこし協力隊制度の導入に尽力した安達さんと、現在協力隊のサポートに奔走する大古田さんに、お話をうかがいました。
※人口減少によって存続が困難になると予測されている自治体
View more
-

- 日本一の公民館が目指す、住民が主役の地域づくり
- 文:高田江美子 写真:鈴木宇宙
「公民館」という場所に対して、どんなイメージを持っていますか?
あまり馴染みがない方もいれば、よく利用するという方もいるでしょう。本来、公民館とは、地域住民にとっての学習拠点であり、交流の場としての役割を果たす場所。
公民館本来のあり方に立ち帰り、住民とともに歩む地域づくりをおこなうのが、宮城県白石市の斎川公民館です。取り組みが評価され、全国に14,281館※ある公民館の中から、文部科学省の第72回優良公民館表彰で「最優秀公民館」を受賞しました。
※平成30年度社会教育調査より
公民館で活動の中心となり奔走する、斎川まちづくり協議会会長の畑中さん、事務長の佐藤さん、白石市役所の佐々木さんにお話をうかがいました。
View more
-
- 日本一の真狩ゆり根を100年続くものに。小さな村の大きな挑戦
- 文:高橋 さやか 写真:髙橋 洋平
羊蹄山の麓にある小さな村、真狩。肥沃な大地と清らかな水に恵まれた地の利を生かし、農業が盛んな村です。なかでも名実ともに日本一を誇るのが「ゆり根」。収穫まで6年もの歳月を要し、大切に育てられます。真狩村を支えてきたゆり根生産のはじまりと、未来に続く物語。ゆり根農家の田村豊和さん、長船寛さん、武田竜太さんと、真狩村産業課長の酒井さんにお話を伺いました。
View more
-

- 子どもの豊かな発想が育むニセコらしいまちづくり
- 文:浅利 遥 写真:斉藤 玲子
ニセコが人々を魅了するのは雄大な自然だけではありません。
自然の美しさを楽しむグリーンシーズン、パウダースノーと戯れるウィンターシーズン。国内外から訪れる多くの人々の心を掴むニセコ町を支えてきたのは、町民ひとりひとりの行政参加でした。
View more
-

- 誰もが輝く村、猿払へ。地元愛を胸に挑み続ける地方公務員マーケター
- 文:三川璃子 写真:原田啓介
ホタテ漁が盛んに行われる海と、酪農地の緑に囲まれた最北の村、猿払。ここには現在2,675人の村民が住んでいます。
「誰もが輝ける場所がある」
村民が輝く場所を守り、広げるため、猿払村役場は旗を上げ続けています。
この村で生まれ育ち、大好きな村のために挑戦を続ける一人の職員がいます。企画政策課の新家拓朗さん。猿払への愛と、活動に込められた想いを伺います。
View more
-

- 赤ちゃん誕生の感謝を形に。「町の資源」が羽幌の未来につながる
- 文:三川璃子 写真:原田 啓介
生まれたばかりの赤ちゃんは、1日の大半を抱っこと「布団」で過ごします。それだけに赤ちゃんにとって、布団は大事なもの。
「羽幌に産まれて来てくれてありがとう」
そんな想いを形に、羽幌町では新生児に焼尻サフォークのめん羊布団をプレゼントする事業を行っています。かつては、産業廃棄物として捨てられていた焼尻サフォークの羊毛。この羊毛が、赤ちゃんも安心して使える町の資源になるまでには数々の試行錯誤が必要でした。
羽幌の子どもたちの未来を考え、資源を守り続けている緬羊工房の本間範子さんからお話を伺いました。
View more
-

- 最北のイチゴの産地へ。新たな産業の歴史がはじまる
- 文:立花実咲 写真:原田啓介
日本全体の課題、人口減少。その減少速度は、地域によって違います。猿払村はホタテの稚貝放流事業によって雇用が安定し、人口の減り方はゆるやかになっています。
View more
-

- 獲り尽くして消えたホタテ。どん底から日本一の漁獲量を誇る村への復活劇
- 文:立花実咲 写真:原田啓介
「人間は神々と力を競うべきでない 人間は自然の摂理に従うべきだ」
この言葉は、オホーツク海をのぞめる道路沿いに建てられた「いさりの碑」に、刻まれています。
View more
-
- 33年の歩みを未来へつなぐ 持続可能な町に向けた東京理科大学と長万部の挑戦
- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子
海もある。山もある。あたたかい人たちがいる。
渡島半島内浦湾に位置する長万部町。
札幌と函館の中間にあるこの町は、古くから交通の要衝として栄えてきました。「自然豊かな環境で人間性を育む教育を」と願った東京理科大学(以下、理科大)がこの地にキャンパスを構えたのは、1987年のこと。33年にわたる大学と町とのつながりは今、町の未来づくりへと歩みを進めています。
View more
-

- コミュニケーションを育むのは1冊の本から 家族をつなぐブックスタート
- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子
読書離れが叫ばれて久しい中、「読書のまち」としての取組みを20年以上つづけてきた恵庭市。全国にさきがけて導入したブックスタートをはじめ、小中学校への図書館司書配置、まちじゅう図書館など、独自の施策をうちだしてきました。
お話をうかがったのは、ご自身のお子さんがブックスタートの一期生という、恵庭市教育委員会教育部読書推進課課長の黒氏優子さんです。
View more
-

- 市民の情熱にまちが動いた 花を素材につくりあげた時が経っても美しいまち
- 文:高橋さやか 写真:斉藤玲子
「花のまち」として、全国的に知られる恵庭市。「恵まれた庭」という地名にふさわしく、花と緑で彩られたまちは、市民が中心となり長い時間をかけてつくられてきました。
人の手がかかる花は、景観を美しくするだけでなく、関わる人の間にコミュニケーションを生み、まちを息づかせてきたのです。
View more
- ホーム
- プロジェクト