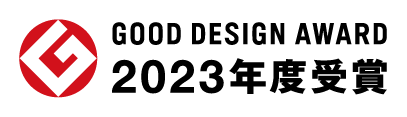日本一の真狩ゆり根を100年続くものに。小さな村の大きな挑戦
真狩村プロジェクト
文:高橋 さやか 写真:髙橋 洋平
羊蹄山の麓にある小さな村、真狩。肥沃な大地と清らかな水に恵まれた地の利を生かし、農業が盛んな村です。なかでも名実ともに日本一を誇るのが「ゆり根」。収穫まで6年もの歳月を要し、大切に育てられます。真狩村を支えてきたゆり根生産のはじまりと、未来に続く物語。ゆり根農家の田村豊和さん、長船寛さん、武田竜太さんと、真狩村産業課長の酒井さんにお話を伺いました。

日本一のゆり根の村
ほくほくとした食感とやさしい甘みのあるゆり根は、高級食材として、和食店で欠かせない存在です。北海道が日本全体の生産量の98%を占め、なんと4割が真狩村で生産されています。料亭などで使わるため、主に関西方面へ出荷されるという、ゆり根。なぜ北海道の小さな村で盛んに生産されるようになったのか、背景を紐解いていきましょう。
ーー真狩といえば「ゆり根」のイメージをもってきました。日本一の産地になったのには、どういった背景があったのでしょう?
酒井:ゆり根の歴史は古いんですよね。北海道では大正時代に和田伊三郎という人が、本州に自生していた小鬼ゆりから、増殖栽培に取り組んだのが始まりとされています。真狩村では、昭和36年に斎藤行雄さんという方が、自家用栽培していた在来種の増殖を試みたのがルーツです。食用ゆり根に目をつけたのは先見の明ですよね。

酒井:さらに先代の農家さん達が広めていこうと、食用ゆり根に特化していきました。昭和41年には真狩村ゆり根生産組合が設立され、本格的な生産がスタート。真狩のゆり根生産の唯一無二なところは、JAで培養していることです。試験管で病気を持たない種を培養することで、一大産地として確立可能なスタイルをつくったんですね。

ーー当時、ゆり根に着目したのはなぜだったのでしょうか。
田村:真狩村は、ほかの地域とくらべて耕作面積が少なかったので、一戸あたりの収入を上げるために、高級食材であるゆり根に着目したんです。
長船:土地が肥沃なことも、ゆり根との相性が良かったんでしょうね。当時は今とは生産方法にも違いがあったと思いますが、収穫には早くても3年くらいはかかったと思います。
酒井:ほとんどの作物は、春に植えて秋に収穫して出荷するわけでしょ。ゆり根は、早くて3年。今は5〜6年かけてつくってるんだよね。最初の人たちはよくやったよね。
田村:そうですね。全部が全部出荷できるわけじゃないし、ロスも多かったはず。忍耐強かったんでしょうね。

ーーゆり根の生産には5〜6年もの歳月がかかるとは、本当に驚きました。手間と根気が必要な作物なんですね。
田村:そうですね。ゆり根の生産は、まずJAの施設で試験管で種が栽培されます。2年目からは僕たち生産者の畑に植えて、一度ゆり根を作ります。2年目の春にゆり根を掘り起こして、ひと回り大きく成長したものを別の畑に植え替えます。その年の秋には、春に植えたゆり根を掘り起こします。ここで、ようやくピンポン玉くらいの大きさ。これを冬期間保存して、つぎの春まで寝かせます。
長船:3年目の春は秋に掘り起こしたゆり根のりん片をばらして、畑に植え替え。 秋はまた畑から掘り起こして、春まで寝かせます。これを4年目、5年目と繰り返していって、6年目の秋にようやく出荷です。
その間、ゆりの花が咲くと根に栄養が行き届かなくなるので、花のつぼみはすべて手作業で摘み取ります。
ーー聞いているだけで気が遠くなりそうです。ゆり根を生産する上で大切にしていることありますか?
田村:ゆり根はデリケートで病気に弱いので、気を使って育てていますね。6年間植え替えをするので、畑の面積も必要だし手間もかかります。農業は機械化が進んでいますが、ゆり根は別。少しでも傷つくと、そこから傷んで変色してしまいます。土を掘り返すのは機械になりましたが、植え付けも収穫も手作業です。
武田:ゆり根は繊細で扱いに慎重さがもとめられますが、手間をかければその分いいものができます。難しさもありますが、やりがいになってる部分でもありますね。
長船:僕は畑づくりを大切にしてますね。有機系の肥料を使ったり。年によって気候が変わるで、不安定な中でもクオリティを保つための努力はしてます。品質が高い人に生産方法を聞いたりして。真狩のゆり根農家は仲が良いので、情報交換しながら、地域全体でより良いものをつくっていこうという姿勢で取り組んでいます。
田村:天気とかいろんな条件で、どうしても良い年悪い年ってあるので、品質を保つ難しさはありますね。昔は情報交換が難しいこともあったみたいですが、今はみんなで「真狩ブランド」を向上させていこう、という共通認識です。

ゆり根をもっと身近に
長い月日をかけて、丁寧に育てられるゆり根。和食店などの需要はあるものの、一般家庭ではまだまだ身近な食材とは言えません。生産者の皆さんとしては「もっと身近に感じて食べてもらいたい」そう。若い世代を中心に北海道内外でのPR活動も積極的におこなっているといいます。
田村:若い世代を中心に活動している、ゆり根青年部というのがあるんです。研修やPR活動の実施、出荷先である関西への視察なども。加工の現場や、実際に料理として提供してくれているお店に行くと、生産者側としては励みになります。若い人が意欲を持って取り組めるように、村やJAが支援してくれて。こうした活動がゆり根生産の成長にも繋がってるのかなと思いますね。
長船:北海道内に限らず、道外にも赴いてPR活動をしていました。コロナの前は関西とか石川県にも行ってましたね。
田村:真狩の道の駅にも、ゆり根を出しています。1年を通して販売できるように、加工品やスイーツなども用意して。ゆり根をもとめて来てくれる人がいるので、切らさず提供できるように努力してますね。
長船:僕も道の駅ができた2005年から関わっています。業者さんと協力しながらゆり根のスイーツを開発したり。農家ごとで味が違ってくるので、ゆり根の食べ比べをやったり。「ゆりンピック」って名前つけてね。
ーーゆりンピック!アイディアはどこからきたのでしょう?
田村:道の駅に携わっていたメンバーが中心になって、アイディアを出しました。最初は、じゃがいもの食べ比べだったんだよね。この辺はゆり根だけじゃなくて、じゃがいもも生産しているから。MKP(マッカリポテト)総選挙といって、2021年も開催しています。
ゆり根でもやったら面白いんじゃない、ということで、ちょうどロンドンオリンピックの時期だったこともあって「ゆりンピック」銘打って開催しました。
長船:サッポロファクトリーという大きな商業施設を借りて、ゆり根の販売会と試食会を実施しました。3年くらいやったのかな。

ーー大きなイベントを開くにあたって、全体のまとまりをつくるのは大変じゃなかったのでしょうか。
田村:みんな「おもしろいことやろう」と言うと、「いいね」という感じ。
長船:とはいえ、僕らだけの力ではできないので、役場やJAにも協力をお願いして。ワイワイと盛り上がって、ホクレンさんやサッポロビールさんが協賛してくださり、北海道庁と北海道開発局も後援してくれて、さまざまな方の協力で実現しました。
田村:生産者と役場とJAが、ひとつになるきっかけにもなりましたね。それまでも協力体制はありましたけど、ひとつの大きなイベントに向かって、みんなが一丸となったことで、より繋がりが強くなった気がします。
ーーイベントではどんな反応がありましたか。
田村:それまで「ゆり根の食べ方を知らない、食べたことがない」という人が多くて。北海道は一大産地のなのに、ゆり根が身近な存在じゃないということが悲しかった。大きなイベントだけじゃなく、地道にPR活動を続けていったことで、真狩のゆり根の知名度が上がったのはうれしいことですね。
長船:それ以降、北海道内でもゆり根を食べてくれる人が増えてきてる感じがします。
田村:道内の人が買って、本州に送ったりね。

農業が抱える高齢化と後継者不足
地域一丸となって盛り上げている「真狩ゆり根」というブランド。若い世代の活躍もあり、身近な食材へと、少しずつ知名度も向上してきています。一方で、多くの農村地域が抱えるのが、高齢化と後継者不足という課題です。
ーー高齢化と後継者不足について、真狩村やゆり根生産においてはいかがでしょう。
酒井:世代にもよるよね。若い人が後を継いでいる農家さんもいるけど、後継者不足・高齢化は真狩にもあります。高齢でやめてしまう人がいるのは、寂しいですね。せっかく日本一の産地だから、「続けて欲しいな、これ以上減らさないで欲しいな」という気持ちはあります。今後の10年見据えた時に、現在140戸くらいある真狩の農家は、100戸くらいになっていくのかな。
田村:真狩では離農した農地は、ほかの農家の人が買い取るので、農家の戸数が減っても耕作放棄地は生まれないんですよね。だから、今のところ1戸あたりの耕作面積は増えていってる状態。でも、離農した土地がさらに増えていくと限界はあるのかなと。
酒井:昔の倍以上の面積になっているから、これ以上増えたら寝ないで働かなきゃいけないでしょう。作れる作物も限られているし。
田村:1戸あたりの耕作面積が増えると、手間のかかるゆり根から離れる人が増えていくのかな。もっと効率よく作れるものにシフトしていく人も、出てくるかもしれない。

ーーゆり根は手間もかかるし、寒い時期の作業など大変さがある中で、農家の皆さんが続けていこうという気持ちはどこからくるんでしょう?
田村:今の一大産地としての真狩は、先人たちの苦労によって築かれたもの。だから、僕は品質の良いゆり根をつくり続けていきたい、という気持ちが強いですね。今の段階では、この先の10年を見据えた時には変わらず、ゆり根生産者としてがんばっていきたいです。
長船:大変さはありますけど、その分働ける期間も長く安定して続けていけます。真狩で生まれ育ったから、日本一のゆり根への誇りもありますし。
武田:僕は茨城出身なんですが、せっかく真狩に来て農家をやっているんだから、「真狩の代名詞であるゆり根の生産に携わっていたい」という気持ちは強いですね。

ゆり根生産の歴史を100年に
先代が培ってきた真狩のゆり根を受け継ぎ、裾野を広げていく若い世代。日本一の看板を背負うからこそ、手間や大変さも力に変えて守っていきたいと、未来を見据えます。
ーーこれから真狩のゆり根をどうしていきたいですか。
酒井:ゆり根の産地としてNo.1なのは、誇れること。60年に渡って、先代の人たちが守ってきたゆり根だから、これからも大事にしていきたいですね。役場としても協力し支えていきたいと思います。もっともっと村をあげて、日本一のゆり根としてPRしていきたいです。
長船:ゆり根がもっと身近な存在になるよう、食べ方や、調理の仕方も含めて普及していきたいですね。マッカリーナのシェフや、地元の料理店も一緒になって盛り上げてくれてるんで。全道的にも全国的にも、ゆり根がメジャーな作物になっていくように。
武田:個人的な夢としては、子どもに「継ぎたい」と思ってもらえるような姿を見せたい。農業楽しそうだなとか。子ども自ら「農家をやりたい」と言ってもらえるように、とにかく、一生懸命ゆり根を生産していくことですかね。
あとは、ゆり根の認知度がまだ低いので、もっと知って食べてもらえるとうれしい。僕らは質の良いゆり根を作って、送り出していくので。
田村:日本一ってなかなか簡単になれるものじゃないですよね。2021年でゆり根生産のスタートから60年。100年目指していかなきゃ。
なかなか簡単にはじめられる作物じゃなくて、技術も必要なので、今生産してる人たちがしっかりやってくしかない。
おいしいゆり根を、味も生産量も日本一を守っていけるように切磋琢磨していきたいですね。

インタビューの合間にも「ゆりンピック、またやったらいいんじゃない」「道の駅にこんな商品があったらいいよね」と、和気あいあいと「ゆり根トーク」に花が咲いていたみなさん。ほかの地域には負けられないという、気概と誇り、ゆり根への愛が感じられました。
長船さんが「お土産に」とくださったゆり根は、こぶしのように大きく立派。教わったアヒージョにしていただいたら、ホクホクとした食感とやさしい甘さでワインにピッタリでした。名実ともに日本一のゆり根。白い宝石は食卓にやさしい華を添えてくれることでしょう。