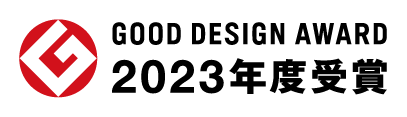変わり種商品とSNSで伝統の白石温麺に新風をおくる、革新のはたけなか製麺
白石市事業者の想い
文:高木真矢子 写真:阿部一樹
400年の歴史を持つ、白石温麺(うーめん)の産地として知られる宮城県白石市。明治23年(1890年)創業の株式会社はたけなか製麺は、伝統を守りながらも、時代の変化を敏感にとらえ、独創的な商品で市場を切り開いています。
広報・食の安心安全にたずさわる執行役員の佐藤祐二さんに、はたけなか製麺のこれまでの歩みと、変化する消費者ニーズに合わせた商品開発について、うかがいました。

畑の中から始まった135年の歴史
ーーまずは、はたけなか製麺について教えてください。
佐藤:はたけなか製麺の歴史は、明治23年(1890年)にさかのぼります。創業当時は工場の周りが一面の畑だったことから、「畑の中のうーめん屋さん」と呼ばれ、地域の人々に親しまれていました。その愛称がそのまま社名となり、今日まで受け継がれています。
手延べ温麺を製造する小さな工場からはじまり、信用を第一に掲げて、地元白石のお客様に愛されながら成長してきました。

ーー“はたけなか製麺ならでは”の白石温麺の特徴はありますか?
佐藤:うちの麺は他社より太いのが特徴です。また、麺生地を一度熟成させた後、麺帯にした状態でさらに熟成ボックスに入れる「二段熟成」も、おいしさのヒミツです。ボックス内では温度と湿度を一定に保ち、20分間寝かせることで、麺肌がとってもなめらかで、「はたけなか」ならではの独特のコシが生まれるんです。
使用する小麦粉にもこだわり、特に「旨さ覚悟」シリーズには手打ちうどん専用粉を使用。それを乾麺化する技術は、食品産業新聞で技術功労賞を受賞しました。

現在、はたけなか製麺では国産小麦を使った商品開発にも力を入れています。北海道産小麦の確保では、日清製粉との協力関係が鍵となりました。
佐藤:過去に製造で課題があった際、日清さんに工場を視察いただき、課題の分析や社員教育をしていただいたのです。そうした関係構築があったことから、日清さんが北海道産小麦を導入しはじめた初期の段階から、「多少コストが高くても、おいしさにはこだわりたい」という思いで、取り入れてきました。
2017(平成29)年には東北大学大学院農学研究科との産学連携で開発した、北海道産小麦100%の「無塩ZERO温麺」も開発。食塩を使用しない製麺技術で作られた画期的な商品は、地域特産品と大学の技術が融合した成果として、農林水産大臣賞を受賞しました。

佐藤:これまで製麺には食塩が必要不可欠とされていましたが、東北大学の産学連携プラットフォームを活用し、食塩不使用でも品質を保つ技術を確立しました。腎疾患や心疾患の方にも安心して食べていただけます。
北海道産小麦を使用し、ゆっくり乾燥・熟成させることで、小麦本来の味と風味を楽しめるように工夫しました。減塩を心がけている方や、お子さんのいる家庭からも「安心して食べられる」と好評です。
5代目会長の決断ーー茶そばで切り開いた新たな市場
時代とともに市場環境は大きく変化しています。人口減少による需要の縮小、コンビニやスーパーでの価格競争、消費者の嗜好の多様化。
伝統的に白石温麺を手がけてきた はたけなか製麺でも、時代の変化に合わせ、2010年(平成22年)5代目に就任した佐藤秀則社長(現・会長)が大胆な商品開発に乗り出しました。
2015(平成27)年に手がけたのが、後に大ヒット商品となる「ぜいたく茶そば」の開発でした。
ーー人気商品である「ぜいたく茶そば」の開発経緯を教えてください。
佐藤:ぜいたく茶そばは、静岡県の標高600メートル以上で栽培される高級茶葉「天竜抹茶」をぜいたくに配合しています。鮮やかな緑色と香り高い風味が特徴で、ご好評をいただいています。
ーーパッケージにもこだわりが感じられます。
佐藤:ええ。ぜいたく茶そばに使用している天竜抹茶は、世界緑茶コンテストで2度金賞受賞した神奈川県の茶師・佐々木健さんに監修してもらいました。その茶師の写真をパッケージに使用し、作り手の顔が見えるようにしたのもこだわりの一つです。

「ぜいたく茶そば」は発売から10年で1000万食を売り上げ、ドンキホーテやOKストアなどでPB商品として展開されるまでに成長。今では温麺と並ぶ主力商品に成長しました。
ーー他にも変わり種商品を開発されていますね。
佐藤:特に注目を集めているのが「手おろし長芋そば」です。
麺に浮いている白い粒は長芋の塊で、青森県の五戸産の長芋を使っています。生のとろろを仕入れて麺にするのは、製麺技術としては非常に難しい。工場長はよくぞ麺にしてくれたな、と思います。
商品開発には苦労もありました。「麺になるか」「売れるか」そして何より「おいしいか」。この3つをクリアするために、毎回試行錯誤しています。
「なかなか麺にならないな」と苦しみながらも、楽しんでいます。


地震という試練ーー支えてくれた取引先との絆
温麺にとどまらず商品の幅を広げ、順調に見えた経営に大きな打撃を与えたのが、2021(令和3)年と2022(令和4)年に相次いで発生した福島県沖地震でした。製造にも大きな影響を受けたといいます。
ーー地震が起きた際はどういった状況はだったのでしょうか?
佐藤:すでに製造していた在庫の商品が崩れて、バラバラの状態で地面に散らばってしまいました。崩れた1万ケースもの備蓄在庫を仕分けして、再度製造し直す。非常に厳しい状況でしたね。
翌年にまた地震があった時は『またか』と思いました。今度は商品だけでなく、原料の小麦粉大袋も倒れて倉庫のシャッターを破損。2011年の東日本大震災より被害が甚大と思えるほどでした。

ーーその状況からどうやって立ち直っていったのでしょうか?
佐藤:社員はもちろんですが、お取引先やお得意様が応援に来てくださったんです。宮城県内だけでなく、わざわざ北海道から来てくださった方もいて・・感動しましたね。
主要な設備は幸い無事だったので、みんなで協力して、1〜2日で復旧作業を終えられました。本当にありがたかったです。
その後は宮城県の支援も受けながら、設備の修復を進めました。この経験を通じて、地域のつながりの大切さを改めて実感しました。
地震からの復旧を果たし、会社も新体制へと移行。長年にわたり商品開発を主導してきた佐藤秀則社長から、2024年営業の生え抜きである大友社長へとバトンが渡されました。
白石市の温麺業界全体にも大きな変化が生まれています。
知名度の壁を越えてーー仲間とともに挑む新たなステージ

2023(令和5)年に放送された「秘密のケンミンSHOW」では、白石温麺が大きく取り上げられました。9センチという短さ、油を使わない製法、江戸時代から続く物語。これらが全国の視聴者の心を掴みました。
ーー放送後の反響はいかがでしたか?
佐藤:放送後、関東圏からの受注が非常に増えました。全国の方に白石温麺の存在を知ってもらう、大きなきっかけになった一方で、まだまだ知らない方が多いのも事実です。
スーパーの棚を見ると、温麺は背が低いので一番上にちょこんと置かれているだけ。どうやって気づいてもらうか、日々考えています。
こうした知名度の課題に対し、佐藤さんは10年前から独自の取り組みを続けています。きっかけは同級生であるきちみ製麺・木村さんの存在でした。
ーーどのようなきっかけから、今のSNS活用まで至ったのでしょうか。
佐藤:木村さんが『めんたろう』としてTwitterで活発に活動していたのを見て、これからの時代、SNSは必須だと感じました。でも同じSNSで戦うのは違うな、と。Instagramに料理を載せてみようと考えました。
料理は苦手でしたが、自分で料理してレシピを考え、投稿を続けて10年。今ではSNSで素敵な投稿をしている方に(温麺の)アンバサダーとして協力していただいたり、クックパッドに100以上のレシピを掲載するなど、発信の幅を広げています。

同級生だった木村さんとの縁は、やがて業界全体の連携へと発展。40代の若手たちが「白石うーめん応援団」を結成しました。
ーー他社との交流によっての変化はありましたか?
佐藤:みなさんと勉強会後の飲み会で語り合ううちに、白石温麺業界全体で協力する必要性を強く感じました。今では「おもしろいし市場」での試食販売や、市内の保育園児たちへはうーめん体操を通じて、普及活動を展開しています。品質管理やSNSの発信方法も情報交換し、みんなで今後の構想を練ることもあります。
岩手のわんこそばや冷麺、秋田の稲庭うどんのように宮城県全体で『宮城県の麺』として推進できるようにしたい。例えば、白石から出て行った人たちが、ふるさと納税を通じて温麺を贈答品として活用してもらったり。地元への恩返しと大切な人への贈り物が同時に叶う、素晴らしい仕組みだと思うんですよね。
白石温麺を日本全国、そして世界へ

ーー海外でも販売を展開されているとのことですが、今後のについてはどのようにお考えですか?
佐藤:温麺は9センチと短いので、すすらなくてもいい。ショートパスタのような感覚で、世界中の人に楽しんでもらえると思います。これまでの縁を大切に、取引先と連携する形で進めていくつもりです。
海外への広がりという意味では、工場で働く外国人の存在も大きいです。
ベトナムとインドネシアからの実習生はみんな本当に勤勉で、日本人スタッフとも仲良く働いてくれています。昨年には、ベトナムから来た男性と女性のスタッフが、遂に結婚したんですよ。ベトナムから結婚式の写真を送ってくれました。
技能実習の彼らが母国に帰った時、「はたけなかで温麺を作った」と紹介してもらえたらうれしいですね。それも世界への広がりの一つだと思います。

佐藤:お客様から『おいしかった』という言葉をいただく時が一番うれしい。日々の疲れが飛ぶような、そんな瞬間です。その言葉のために、これからも挑戦を続けていきます。
「白石に戻って温麺を食べたら、もう白石温麺しか食べなくなるんですよ」。秋田では稲庭うどんを食べていた佐藤さんが、Uターン後に再発見したのは、9センチの短い麺に込められた無限の可能性と、歴史ある地元・白石の魅力でした。
5代目が切り開いた道を、新体制のもとで社員一丸となって歩み続けているはたけなか製麺。地震という困難を乗り越えた取引先との絆、仲間へと変わった地域の温麺会社との連携、SNSで広がるファンとのつながり。
人と人とのつながりこそが、はたけなか製麺の原動力となっています。伝統の白石温麺を全国、そして世界へと届ける挑戦は、これからも続いていきます。

Information
株式会社はたけなか製麺
〒989-0276 宮城県白石市大手町4-11
TEL:0224-25-1313