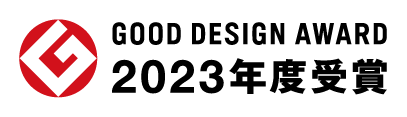語り手と読み手の世界に寄り添う。「一緒に歩く」から始まるライターのあり方
Takibi Connect 編集部より
取材・文:三川璃子
記事づくりの現場にもAIの力が入り始めた今でさえ、「取材」は人にしかできない大切な営み。語り手と向き合って言葉を交わし、心の奥にある本音をすくい上げる——
それが私たちライターの仕事です。
「インタビューは語り手と一緒に歩いていくようなもの」と語るのは、takibi connectでライターとして活動する本間幸乃さん。多くの人の声に耳を傾けてきた本間さんはどんなことを大切にしているのでしょうか。
本間さんのライターとしての営みについてうかがいました。
「対話」とは語り手の世界で共に歩くこと

インタビューは「inter(~の間) + view(見る)」という二つの単語が組み合わさってできた言葉。語り手と聞き手の二人が同じ景色を見ながら、互いを知っていく。本間さんはインタビューを通して人と人との「対話」でしか見られない世界を大切にしていました。
ーーインタビューはある意味、「対話をする」ことだと思うのですが、「対話」において何を心がけてきましたか?
本間:「対話」ってなんだろうと考えると、ただ「質問して答えてもらう」のとは少し違う気がします。私自身が“対話”を実感できたのは、以前働いていた福祉の現場でした。特に知的障害のある方と一緒に働いていた経験が大きかったですね。
ーーどんな経験だったんですか?
本間:知的障害のある方は言語だけじゃない、それぞれお気に入りのコミュニケーションがあるんですよね。例えば、手を受話器に見立てて「もしもし」と話したり。私も同じ仕草で相手に合わせて話すと、言葉を超えた部分でお互いに思いが通じる瞬間があったんです。
相手の世界に入り込んでみた経験が、今のインタビューの根っこになっている気がします。

ーー取材だと時間が限られるので「相手の世界に入り込む」ってなかなか難しいなと、ライターをしていて感じます。何かコツはあるんでしょうか?
本間:相手の世界に一気に入り込める、特別な魔法の言葉や問いはなくて、対話という道のりを一緒に歩いていると少しずつ入れる感覚で、「話しているうちに、自然と」ですね。
ーー「一緒に歩く」というのは、素敵な表現ですね。
本間:私、散歩が好きなんですが、対話もまさに「散歩」だと思うんです。同じ道を一緒に歩くうちに景色が見えてくる。でも同じ景色を見ているようで、目に入るポイントは人それぞれ違います。
対話は、そんな散歩の中で気になったものを「問い」として交わすような感覚です。
散歩途中に相手が立ち止まれば、自分も立ち止まる。前職で非言語コミュニケーションを意識したように、相手のちょっとしたしぐさや表情もキャッチして、歩調を合わせるのも大切にしています。

ーー過去に印象的だった取材(対話)はありますか?
本間:特に印象に残っているのが、北海道岩見沢市にある「こぶ志窯」の山岡千秋さんへの取材です。山岡さんは焼きものへの情熱溢れる方で、約80年にわたる窯元の歩みをたっぷり聞かせてくれました。器好きの私にとっては、どのお話も興味深いものばかりでしたね。
1時間半くらい話した後にようやく、これまでの山岡さん自身の話になって。歩みをたどる中で「今までは家にこもって作品づくりばかりだったけど、家業を守るために営業を始めたんだ」と語ってくれたんですよね。
私が「営業を始めたのはいつ頃ですか?」と聞いたら、「40代だね……いや、今思うとあの時は“内から外に出た”、自分にとって大事な時期だったんだな」と、ふいに気づいたように、山岡さん自身もまだ知らなかった答えにたどり着いたんです。
語り手も知りえなかった「答え」をゆっくり一緒に歩くことで見つけられた。あの瞬間に立ち会えたことは何より嬉しかったですね。

ーーインタビューは、語り手がすでに知っている「答え」を聞くだけではなく、お互いに知らない「答え」を探す作業なのかもしれないですね。
本間:夢中で走り続けてきた人だからこそ、自分のことってなかなか自分で気づけない。「なぜだろう」って立ち止まって考える機会がなかったりする。
でも対話を通して一緒に道を歩いてみると、「そういえばそうだったね」と何かを思い出してくれることがあるんです。散歩のなかで見つかる本音や気づき。それをキャッチするのがライターの仕事であり、面白さかなと思います。
自身の読書体験が記事に活きていく
「取材時間は語り手への興味が止まらなくて、長くなっちゃいます」と本間さん。語り手の世界に入り込んでいるからこそ、時間を忘れてしまう取材が多いのだろうと想像できます。そんな本間さんは、受け取った語り手の言葉をどのように記事にしているのでしょうか。

ーー語り手の言葉を読み手に届けるために意識していることはありますか?
本間:「読み手としての自分を鍛える」ことです。私自身が読み手の気持ちを1番に理解すべきだと思っています。
私にとって本を読む楽しさは「文章を通して、世界の見え方が変わること」です。「こんな世界もあるんだ」と感じた読書体験があるからこそ、私の記事を読んだ人にも世界が変わる体験をしてほしい。
ーー語り手の思いを大切にしつつ、読み手の世界にも寄り添っているんですね。
届きやすい文章にするために意識していることはありますか?
本間:取材で受け取った言葉や感情って、例えると食材そのもの。だから食材をそのまま渡すのじゃなくて「この食材を使って、こんな料理にしてみました」と、差し出すイメージです。
なるべくその素材の味をそのまま出せたらと思うこともありますが、どこまで調理して届けるかは、まだ自分の中で模索している部分でもあります。
読み手に気づきや変化をあたえるような文章を

ーー今後、ライターとしてどう活動していきたいですか?
本間:実はライター以外の肩書きもつくれないかな、と思っています。
「書く」ってものすごく多様じゃないですか。インタビューだけじゃなくて、小説も歌詞も書き物です。これからも誰かの言葉を聞いて、「書く」という行為は続けていきたいです。
ーー本間さんにとって「書くこと」とは何ですか?
本間: 書くというのは、語り手の思いを「言葉」として外に表出させるものだと思います。対話の時の言葉は「音」として現れて、目に見えず消えてしまう。ですが、書くことでその言葉が目に見えて残るものになる。
でも「文字」として現れるのは「文字起こし」の工程で、これは「言葉」とは違うと思っていて、自分が語り手のエピソードを受け取って、どう解釈して、どう届けたいのか。一度語り手の言葉を体に入れて、変換することが「書く」ことなんじゃないかと。
ーー対話で出たエピソードに自分が「何を思うか」を反映させるのは大切ですね。これこそAIではできない、人間の感情があるからこそできることだなと思いました。
変換した「言葉」にはどんな力があると思いますか?
本間:語り手自身が「言葉」を改めて目にすることで、インタビュー時の「気づき」をもう一度振り返ることができる。
そして語り手の思いやエネルギーが宿った言葉は、読み手を癒したり、励ます力になるんじゃないかと思っています。そんな読み手に気づきや変化を生み出せるような記事をこれからもつくっていきたいです。
相手の世界にそっと入り、寄り添いながら一緒に歩く。インタビューとは、ときにその人すら気づいていない思いや変化を見つけていく、本間さんが語る「散歩」のようなことかもしれません。
「インタビュー」や「書くこと」は、情報を得る・伝える技術ではなく、人と人をつなぐ営みそのもの。語り手と読み手の世界を横断しながら、重なり合う部分を創るのがライターの仕事なのだと感じました。