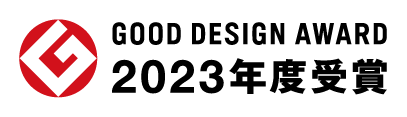「ホーム」=自分を大解放できるつながりの中に。元無拠点女子が見つけた居場所のかたち
Takibi Connect 編集部より
取材・文:本間幸乃
「心から安心できる居場所がほしい」。それは私がずっと抱いていた願いでした。
小さい頃から不安が強く、周囲を気にしすぎる性格から、家や学校でうまく「居場所」を見つけることができなかったのです。
大人になって一人暮らしを始めてからは「やっと自分の居場所を手に入れられた」うれしさを感じました。私にとって居場所とは、物理的・心理的に「安心安全」が守られる場所。単なる「家」を超えた「ホーム」と呼べる場所だと気づいたのです。
takibi connectのライターとして出会った三川璃子(りこ)さんは、かつて「無拠点女子」として、特定の拠点を持たないライフスタイルを実践してきた経歴の持ち主。
「拠点がない」りこさんにとっての「ホーム」とは、どんな場所なのだろう?
居場所を求め、探し続けてきた当事者として聞いてみました。
尊敬で結びつく家族だからこそ「個」でいられる

りこさんは、2019年から2022年まで「無拠点女子」として、全国を移動しながら執筆活動や地域PR、イベントの企画運営などを手がけてきました。
まずは「無拠点」を選んだ理由についてうかがうと、りこさんの家族への想いが見えてきました。
ーー「無拠点女子」を始めたきっかけはなんだったのですか?
三川:会社員からフリーランスへの転向を考えていた2018年に、拠点を持たずに働く「アドレスホッパー」を知って。パソコン1つで全国を飛び回る姿を見て、「こんなことができるんだ!」と惹かれたのがきっかけでした。
ちょうど前年に、私は札幌から福岡へ、父は埼玉に、母は仙台へと、家族の異動や引っ越しが重なり、札幌の実家は手放していたんです。
「実家がない」状況を活かして身軽になった方が、家族に会いに行きやすいんじゃないかと思ったのも、無拠点を選んだ理由でした。
もともと“家族”としてみんなで一緒に過ごすよりも、母や父、弟と個々に関わる方が好きだったんです。「みんなが動けないなら、私が会いに行くよ」くらいの感覚でしたね。
ーー家族だけど「個々」で関わるって面白いですね。それは三川家ならではの教育方針ですか?
三川:おそらく母の影響が大きいと思います。
母は“一人の人間”として人生を謳歌してきた人なんです。子育てや仕事に追われる中でも「自分が楽しむ」ことを諦めない。好きなアーティストのライブにも積極的に足を運んでいました。
私が子どもの頃は、そんな母を周囲では疑問視する人もいたようなのですが・・私自身が大人になって、改めて母の「貫く姿勢」に尊敬の気持ちが生まれたんですよね。
母だけでなく、他の家族にも「自分がやりたいことをやろう」という考えが根底にあります。人として尊敬し合っているからこそ、家族でも「個々」という捉え方になっていったように思います。

「ホーム」には信頼できる「人」が必要
尊敬で結びついているからこそ、それぞれの拠点で自分の人生を謳歌できる。
りこさんの家族のあり方から、「ホーム」=「安心安全な場所」という固定観念が私の中にあったと気づかされました。
「場所」にとらわれないホームもあるのかもしれない。ふとよぎった想いから「安心感」についてうかがってみると、りこさんは考えを巡らせながら答えてくれました。
ーー安心するとか、ホッとする瞬間ってどんなときですか?
三川:そうですね・・あまり意識したことはなかったのですが。カフェで一人になって、ひと息つくときかもしれませんね。
基本的には好奇心が強くて、人に会うことで元気になるのですが、周囲の目や反応を気にしすぎる部分もあるんです。その性格ゆえ、疲れたときには一人で「充電」する時間が必要なんですよね。
ーーホッとするのは、一人でいるときなのですね。
りこさんにとっての「ホーム」は、場所ではなく「時間」‥?
三川:ホッとするときは一人ですけど・・私がホームと感じているのは、自分を「大解放」できる場所。話しているうちに気づきました。
周りを気にしないで、自分が自分らしくいられる場所。この人の前なら感情が溢れてもいい、「何をしても大丈夫」と思える、信頼できる人がいる場所がホームです。
ーー「人」が必要なんですね。
三川:はい。私にとってのホームは道内に3箇所あるんです。八雲町と士別市、そして鶴居村。自分を大解放しても受け止めてくれる、一緒に楽しんでくれる人たちがいるから、めちゃくちゃホームですね。

大切なホームを守り、支えていきたい
りこさんのお話から、私が抱いていた「ホーム」のイメージが解体されていくような感覚に。「安心」を得るための「ホーム」も必要だけど、それだけじゃない。
「安心」と「解放」。私にとっては相反するものに見えていた2つの感覚は、「信頼できる他者」の存在によって、両方同時に得られるのではないかと感じました。
ーー「この人の前なら解放できる」という人たちに、共通点はありますか?
三川:みんな「場」の主ですね。ゲストハウス、オーベルジュ、キャンプサイト、場の形はそれぞれですが、「人を受け入れる」ことをずっと続けてきた人たちです。
お話しているうちに、過去の記憶と「ホーム」が結びついてきました。私、友達の実家によく行くし、以前は上司の実家にも遊びに行っていたんです。
人の実家にいると、ちょっと泣きそうになるんですよね。
食卓にたくさんの料理が並んで、子どもの帰りを歓迎している家族を見ると、言葉にならない感情がこみ上げてくるんです。
もしかしたら私は実家がないことで、ホームを作る人に憧れがあるのかもしれませんね。心の奥では安心できる居場所を求めていたのかも。
だから安心感を生み出す人たちの元に赴いているんだと、今気づきました。
ーーそんな人や場がたくさんあるって素敵ですね。
三川:ありがたいですね。

「以前は自分でもホームとなる場所を作りたい気持ちが強かった」というりこさんですが、今は「動いて場所を見つけていく」スタイルの方が合っているそう。
たくさんできた「ホーム」とのつながりを、今後どのように育んでいくのでしょうか。
三川:私にとって一番悲しいのは、大切なホームがなくなってしまうことです。だからこそ、今後は私のように居場所を求めている人に、場所や取り組みを紹介していくことで、ホームを守り、支えていきたいと考えています。
今までもらってきたたくさんの愛情やエネルギーを、これからは返していきたいですね。
「ホーム」とは、自分を解放できるつながりの中にある。居場所についての新たな定義が生まれたインタビューでした。
りこさんから「解放」という言葉を聞いたとき、これまで私はずっと、大切な居場所を守ろうと、一人で「安心」の壁を築き、閉じこもっていたことに気がつきました。
そこから一歩外に出て、ありのままの自分を他者に見せる。そんな経験から生まれる「ホーム」も感じてみたい。きっと自由と安心が共存する、より豊かな居場所に違いないからです。