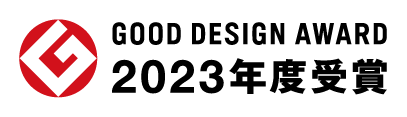アメリカで描いた夢を恵庭で現実に オンリーワン×ナンバーワンでつくりあげた余湖農園の軌跡
恵庭市事業者の想い
文:高橋さやか 写真:斉藤玲子
かっこいい農業、もうかる農業、市民参加型の農業。26歳の頃、研修のためにおとずれたアメリカで見たのは、日本の30年先をいく農業でした。
「いつか自分もこんな農業を形にしたい」ーーそんな想いを胸に、時間をかけて理想を現実のものにしてきた余湖農園代表の余湖智さん。まだ、6次産業化という言葉がなかった時代から、自社商品の開発や流通、観光農園を手がけてきました。約50年にわたる軌跡をたどります。

つくりたかったのは、市民参加型の農園
余湖農園に到着してまず驚いたのは、立ち並ぶ大きな倉庫と広大な畑。楽しそうに選別、梱包する人たちと出荷を待つ野菜たちの姿がありました。
「いまは、ねぎの選別をしてるんですよ。これは・・」とひとつひとつ丁寧に解説してくれる余湖社長。「ここでお話ししましょうか」と、直売所の一角に腰をかけ、インタビューがスタートしました。

ーー想像していたよりも規模が大きくてびっくりしました。これからどういったところへ届けられていくのでしょう?
余湖:北海道内だと、コープさっぽろ、東光ストア、イトーヨーカドーなど、スーパーへの卸ですね。道内に限らず、東京や九州など各地の業者さんと付き合いがあって、いろんなかたちで出荷されていきます。
ーー会社を設立された当初から、スーパーへの卸を?

余湖:まず前段として、単純に野菜をつくって、農協に持って行って売るんじゃなく、市民に直接有機栽培の野菜を届けるという活動に方向転換していったのが30年ほど前。当時は、有機栽培も産直も一般的ではなかった時代ですね。
「市民を巻き込んだ農園にして事業を展開していきたい」という思いがあったんです。
当時の農地法という法律の中では、農業法人に市民が出資するということができなかった。そこで別会社を作って、お金なり労働力なり、市民を巻き込んだ農園にして事業を展開していきました。
方向転換をしたことで、消費者なり、事業主なりが出資して、みんなが参加する農園にかわっていったんです。そこからさらに、個人のお客さんだけでは効率が悪いので、徐々にスーパーへの卸に転換していきました。当時はそれまでのお客さんからの批判もありましたが。
アメリカで出会った理想の農業のかたち

ーー市民参加型の農園にしたいというのは、なにかきっかけがあったのでしょうか?
余湖:26歳の頃、北海道が企画したアメリカでの農業研修ツアーにいったんです。当時の農業は、アメリカと日本で30年の差があった。日本とはくらべものにならない、大型農業。
「もうかる農業、かっこいい農業、市民と触れ合う農業」
自分の理想とする農業の姿がそこにありました。そこからずっと夢に見ていて、少しずつかたちにしいったんですね。
転機は約10年前、以前の農地が遊水池の建設で買収になった時。まとまったお金が入ってきたので、観光農園、6次産業化を手がけようと、投資したんです。国でもまだ、6次産業化という言葉がない時代だったので、はしりですね。
生産、加工、体験農場。ようやくいま、この3つがバランスよく、軌道に乗ってきたところ。災害や社会情勢の変化があっても、3つの柱があるから、どれかひとつ上手くいかない年があっても、ほかの部分で補完できるんです。
アメリカで学んで、ずっとあたためていたことが何十年かたって花開いたんだね。
労働の苦しみよりは、経済的な苦しみの方が大きい
アメリカで見た理想の農業を少しずつかたちにしてきた余湖社長。今では、生産、加工、体験農場が軌道にのった状態ですが、ここまでの道のりは決して平坦ではありませんでした。
余湖:私の両親は、開拓者として佐渡島から恵庭に入植しました。親は悲惨な歴史を持っていてね。満州に開拓者として行っていたんですが、1945年にソ連軍が攻めてきて、佐渡に帰ってきた。故郷では先祖伝来の農家だったんだけれども、満洲に行く際に、次男に権利をゆずったために居場所がなかったんです。それで、第2の開拓民として恵庭にきました。
ーー故郷をおわれる形で恵庭にやってきたのですね。余湖社長は子どもの頃から農家になろうと?
余湖:自分の意思に関係なく、親の命令だから、反対することはできない。お前は長男だからと、当たり前に家のことをやる時代でしたね。

ーー農園をはじめてから大変だったこと、苦労されたことは?
余湖:労働の苦しみよりは、経済的な苦しみの方が大きいよね。
一番の苦労は、昭和56年に56災害といって集中豪雨にあって、野菜が全滅して莫大な借金を背負ったこと。歴史上の大きな出来事ですね。働くことは小さい頃からやってきたので、苦じゃないけど、経済的にうまくいかないのは精神的にも苦しいよね。
56災害とは、昭和56年8月から9月までの豪雨により、石狩川流域に甚大な被害がおよぼされた災害のこと。1ヵ月間に札幌で700mm以上という、年間の約6割にあたる雨が降りました。この豪雨で石狩川流域では8月に2回の大洪水が発生し、石狩川流域全体の被害額は約1,000億円に。当時は「500年に1回の洪水」とも言われました。

経営の要はオンリーワン×ナンバーワン
余湖農園は、まだ有機野菜がめずらしかった時代から地元の消費者の声に応え、有機・特別栽培の野菜作りに取り組んできました。土づくりにもこだわり、自家製の完熟堆肥をたっぷりと畑にすき込み、地力を上げることに力を入れています。
ーー余湖農園で生産されている作物の特徴はどんなところでしょう?
余湖:私がよく言うのは、オンリーワン。
まず、青ネギが全道で一番。丸亀製麺のネギは余湖農園のネギなんですよ。つぎに、セロリ。大根やキャベツだったらどこでも産地があるけど、セロリは競合がないから、そこを狙っていくんです。何年かあたためてきて、「いけるぞ!」という時にパッといくと爆発する。

余湖:ほかにも、年末の三つ葉は30万株で全道で二番目、調理用トマト、土ネギ。土ネギは、土つきのまま出荷するので、その分手間がかからない。
調理用トマトは路地栽培ができて、支柱や、わき芽の処理がいらないんです。生産する側にとって手間がかからないだけでなく、食べる側にとっても、リコピンが生食用の2倍、グルタミン酸が4倍あって、栄養とうま味が豊富なんです。
ナンバーワンとオンリーワンの掛け合わせですね。

余湖:うちは今60品目つくってるんです。一般的には、3品目ぐらいで効率よく作るところが多いんですが、毎年同じ畑に同じ作物を植えると病気になるので、科の違う作物をうまく組み合わせることで、病気を防ぐことができます。
種類が多いということは、それだけ手間がかかるので人手が必要。外国人も積極的に雇用しています。最近はベトナムからの研修生が多いですね。
人種に関係なく、社員が一致団結して仕事にとりくんでくれるのはうれしい。だから、意欲を持たせるように話したり、働けば働くほど報われる環境をつくっていく。チャレンジ精神のある人で固めていくんです。

築いてきたものを未来につなぐ
農業の技術者として、経営者として余湖農園をそだててきた余湖社長。アメリカで描いた夢が形となったいま、今後についてうかがいました。
ーー今後の夢はありますか?
余湖:私が引退しても余湖農園が永続的に営農ができるように、社長業と農業の技術者という立場で、後継者ができてくれると最高です。
子どもが4人いるけど、みんな出て行ってしまっているから。永続的にできるように、私ができることをやっていく。いまはある程度形ができたから、あとは微調整ですね。
おかげさまでふるさと納税も好調。トマトは売り切れますし、今年出したスイートコーンも好調です。大切なのは、お客さんに魅力的な商品と価格の提案。
経営というのは常に動いているから、毎年、前年の反省にしたがってあとは微調整してより人を惹きつけるものを提供していきたいですね。

おだやかな雰囲気ながら、バイタリティにあふれる余湖社長。
「私の特技は、はじめての人とでもすぐ友達になれること。だから、仲間が増えていく。商売だろうとそういう信頼関係が大事」と笑顔でおっしゃっていました。経営者として抜群のセンスをもつ余湖社長のお話に、終始ひきこまれました。「はい、お土産できたよ」と手渡してくださったトマトでつくったトマトソースは絶品でした。

会社情報
㈲余湖農園
〒061-1365 北海道恵庭市 穂栄323
TEL: 0123-37-2774